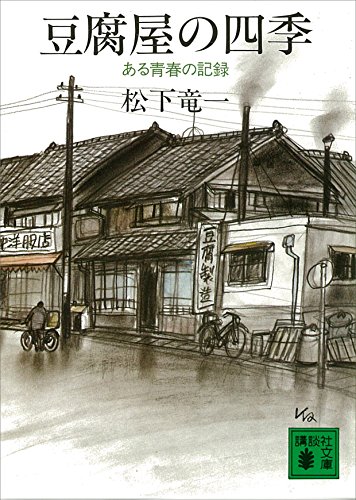「いつか読書する日」という映画を最近見ました。田中裕子演じる独身の50歳の女性は、一人暮らしで牛乳配達とスーパーのレジ打ち、2つの仕事をかけもちして暮らしています。夜明け前に自転車で街を回って牛乳を配達していくその人の姿が、けなげで真っすぐでなんだか胸がいっぱいになってしまって、そのとき、昔読んだ「豆腐屋の四季」のことを思い出しました。子どもの頃は図書館が苦手で、借りた覚えがあるのは高校の図書館にあったこの本くらい。その頃はまだ自分の未来にたくさん夢を見ていたので、進学を家の都合で諦めて豆腐屋を継いだ著者のことを想像すると、悲痛で耐えられないほどの気持ちになったものでした。
今は、勉強や若いころの仕事は、その後の人生で取り戻せると実感してるけど、その頃は一生逃れられない運命のように思えて。学校ってすごく狭い世界で、社会に出る前って半径2メートルくらいまでしか想像力が働かなかったから…。
この本を読み直しながら、何度も涙が出ました。年をとってから読んでもやっぱり、著者の豆腐屋の家族を見ているのは辛い。若くして亡くなった「母」がすべてをつなぎとめていたなら、彼女が生きていた頃はどんなに活気のある明るい家だったんだろう?
貧困と不和のなかで「K市」にひととき家出をした彼が見る映画は「鉄道員」。イタリアの労働者を描いたニュー・シネマです。日本の片田舎の豆腐屋のプロレタリア文学「豆腐屋の四季」は発売されてすぐに注目されてドラマ化もされたけど、映画にならなかったので今はもう見ることは多分できない。
結婚したあとも「毎朝2時」に起きて豆腐を作るのだ。働けど、働けど…。昔はみんなそうやってひたすら働いてたんだよな。
高校生で読んだのは多分最初に発行された単行本で、「相聞」(著者が結婚前に恋人に長年書いて送った愛の歌をまとめて、結婚式の引き出物として配ったものを再録)は入ってなかったんじゃないかな。初々しく純真な恋愛感情に、読んでて頬が赤くなる思いがします。この人の感受性と文才はほんとうに、今読んでも群を抜いていたなと感じます。
このあと著者は豆腐屋を廃業して、死ぬまで文筆業を続けます。「砦に寄る」や「ルイズ 父に貰いし名は」は、文庫になったとき小遣いで買って熱読んだ記憶があって、もしかしたら私の”判官びいき”の傾向は、この人の影響もあったのかもしれません。
去年会社を辞めて早い”半隠居”に入ってから、お金がなかった頃を思い出すことが多くなったけど、節約しようと思うていどで、身を粉にして休まず働き続けるなんてことはもうないと思ってました。何十年も働いたんだから、もう休もう、って。…でも、家族がいるわけでもない私は、家にいると誰の役にもたってない。この本を読みなおして、労働の尊さを思い出してしまったので、もう一度これからの仕事のことを考えてみようかなと思っています。
(1993年9月30日第7刷 講談社文庫 500円)